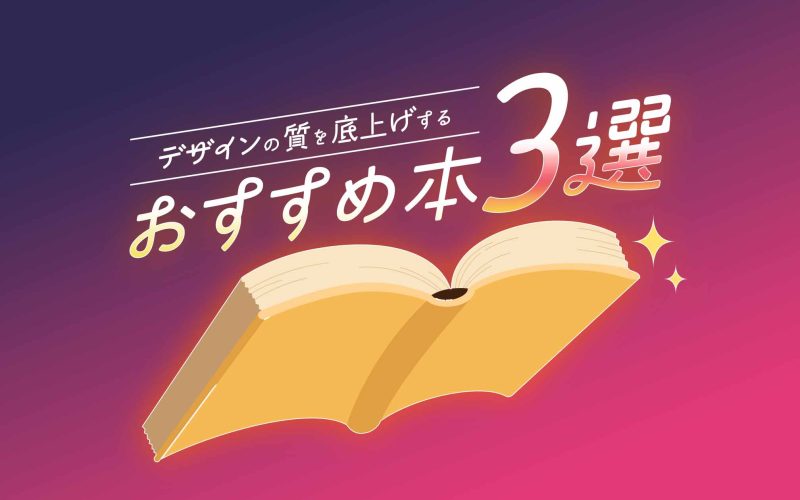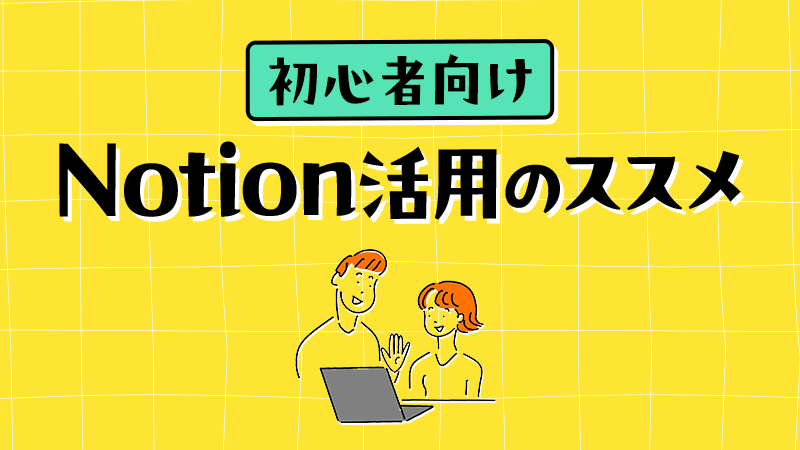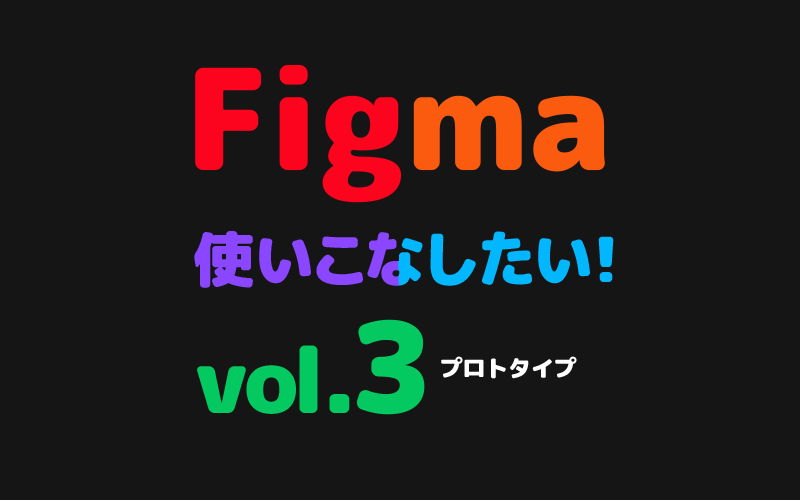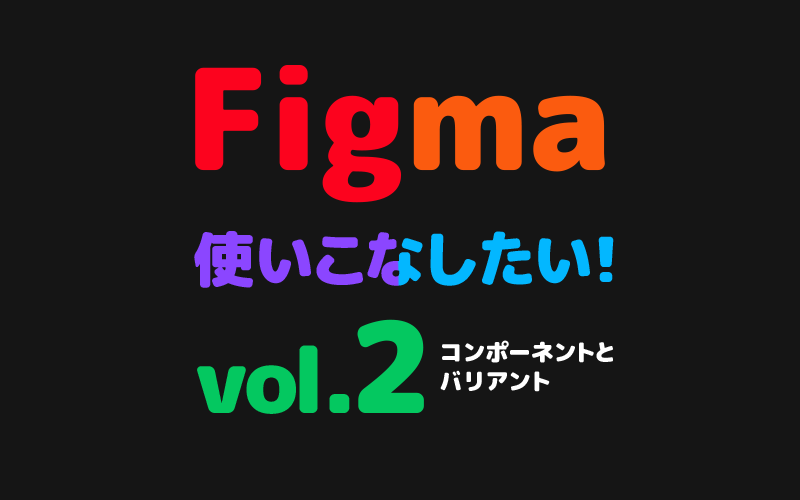はじめに
お疲れさまです。
この記事では、私が大学在学中の4年間で取り組んできたことを紹介します。
特にWeb系のエンジニアを目指している方には、何かしら参考になる部分があるかもしれません。
4年間を振り返ると内容が多く、少し長くなりますが、大きく分けると 「自己探求」「学問」「スキル」「挑戦」 の4つの観点で紹介します。
1年生:自己探求と基盤づくり
大学生活の最初のテーマは「自分を知ること」でした。
高校の恩師の紹介のもと、情報系の大学に入学したものの将来の方向性がまだ明確ではなく、何を専攻するか、どんな分野に進むかも手探りの状態でした。
そこでまずは、部活動やアルバイトなど、いろいろな活動に顔を出しながら「自分は何に興味を持つのか」「どんな環境で力を発揮できるのか」を探しました。
ガーデニング部の活動
元々植物に興味があったという軽い理由で、大学入学時にガーデニング部に入部しました。活動内容は主に敷地内の畑の管理や、季節ごとに学内をハロウィンなどのテーマで設営するなど、学内の環境を整えるものでした。
しかし、私が入部した当初は、コロナの関係で部活動を行うことができず、部員が私と卒業を控えている先輩1人、そして顧問の先生だけという小さな組織でした。自然な流れで私が2年生の時に部長を引き継ぐことになりました。そこからは「この部をもっと活気あるものにしたい」という思いで取り組みました。
まずは、部の存在を知ってもらうために学内掲示やSNSを活用して広報活動を行いました。また、ガーデニングの楽しさを体験してもらえるように、体験イベントや季節の花植えワークショップを企画しました。単なる「畑を管理する活動」ではなく、「人と自然をつなげる活動」 として打ち出したことで、徐々に新入生や他学部の学生も興味を持ってくれるようになりました。
その結果、部員数は私が卒業するころには約40名にまで増加しました。小さな組織を立て直し、持続可能な形に育てられたことは、自分にとって大きな成功体験となりました。ガーデニング部での経験を通じて、「リーダーシップ」「課題解決力」「組織を成長させる工夫」を学ぶことができました。
飲食店でアルバイト
大学に入学した当初、私は人と目を合わせて話すことが苦手でした。そんな自分を変えるために選んだのが、飲食店でのアルバイトです。私はハンバーガーチェーンでしばらく働いていました。お客様と必ず会話しなければならない環境に身を置いたことで、少しずつ人との会話に慣れ、狭かった交友関係の輪を広げることができました。これは大きな自信につながった経験です。
2年生:学問とスキル
資格を取る
基本情報技術者試験など情報系の資格はもちろん自分が興味のある資格を取りました。(マナー検定とか)常に学ぶ意識は大事だったりします。
資格取得は「常に学び続ける姿勢」を育てる機会になり、就職活動においても自分を語る強みになりました。
経営情報学部での学び
私は経営情報学部に所属し、経営学と情報技術の両方を学びました。
経営学の分野ではマーケティングや会計、組織論を学び、情報学ではプログラミングやデータベース、ネットワーク、情報システム論を体系的に習得しました。
学部の特色を活かし、新規事業アイデア系のビジネスコンテストにも参加しました。市場調査や収益モデルを考え、審査員にプレゼンを行う中で、
「技術的に作れるか」だけでなく 「市場で受け入れられるか」「ビジネスとして成立するか」 を考える視点を学びました。
3年生:挑戦と外の世界を知る
3年生では、積極的に外の世界に飛び込み、多くの実践経験を積みました。
学外プロジェクトやハッカソンに挑戦する
大学や個人制作では自分ひとりでプロダクトを作成するということが多いと思いますが、
また、学外ではハッカソンや自主的な開発プロジェクトにも挑戦しました。特にハッカソンでは 短期間で動くサービスを作り上げる という実践的な経験ができました。エンジニアを目指す方なら一度は参加して後悔ないはずです!
主にバックエンド開発を中心としたWebアプリ制作に取り組み、複数のハッカソンにも参加していました。サーバー構築やデータベース設計を通じて、サービスの基盤を支える役割の重要性を学びました。
以下が開発したプロダクトの一部です。
- デジタル名刺交換アプリ
- AIパワポ自動生成アプリ
- 家計簿アプリ
- 出会い系アプリ
- AI音声要約・翻訳Webサイト(120言語対応)
- ラズベリーパイを用いた組み込み開発
- 多数のWebサイト
その一方で、チーム開発の中で「ユーザーが直接触れる部分」であるフロントエンドの表現力が、プロダクトの印象を大きく左右することを何度も実感しました。UI/UXの工夫によって「使いやすい」「また使いたい」と感じてもらえるかどうかが変わる場面を目の当たりにし、次第にその奥深さに惹かれていきました。
そこからは、バックエンドで培ったロジック設計の経験を活かしつつ、Reactなどを用いたフロントエンド開発に力を入れ、フロントエンドの可能性を強く意識するきっかけとなりました。
現在フロントエンドエンジニアという職種に就いていますが、学生時代の経験が今の自分の仕事に直結していると強く感じます。バックエンドの基礎があるからこそ、データの流れやシステム全体を意識したフロントエンド開発ができるようになりました。また、ハッカソンやビジネスコンテストで学んだ「スピード感」や「ユーザー視点」は、実務の場でも役立っています。これからも新しい技術を学びつつ、より多くの人にとって使いやすいサービスを作っていきたいと思います。
早いうちにいろんな企業を見る
私は大学2年生の3月から本格的に就職活動を始めました。早い段階で企業を見て回ることで、社会の動きや働き方の多様性に触れ、自分がどのような環境で成長したいかを考える時間を十分に取ることができました。
説明会や友人との会話を通じて、同じ「エンジニア職」であっても、企業ごとに求められる役割やキャリアの広がり方が大きく異なることを知りました。大規模な組織でシステムの一部を担う働き方もあれば、スタートアップで幅広い業務に関わりながらスピード感を持って挑戦する働き方もあります。こうした比較を重ねる中で、私は「新しい技術を積極的に取り入れ、ユーザーに近いところで価値を提供できる環境」で成長したいと考えるようになりました。
結果として、就職活動を進める中での選択肢や判断基準を明確に持てたことは大きな収穫でした。単に「内定を取ること」がゴールではなく、「自分が納得して長期的に成長できる場を選ぶこと」が重要だと実感しました。この経験が、現在フロントエンドエンジニアとしてのキャリアを歩む上でも、軸となる価値観につながっています。
4年生:自己研鑽と今後について考える
最終学年では、研究と内定者アルバイトを軸に動きました。
卒業研究
私の卒業研究のテーマは、「地域の祭りを特集し、Webサイトに掲載して復興に寄与する」 というものでした。
地域社会では少子高齢化や人口流出の影響で、伝統ある祭りの存続が危ぶまれているケースが少なくありません。特に近年はコロナ禍の影響もあり、祭りの開催自体が難しい状況が続き、地域文化の継承が課題となっていました。
研究の目的は、
- 地域文化をデジタル上で可視化・保存すること
- Webを通じて地域外の人々にも祭りを知ってもらうこと
- 観光や地域振興につなげ、復興の一助とすること
でした。
つまり、単なるWeb制作ではなく、地域社会に役立つ仕組み作りを目指しました。
内定者アルバイトに参加する
4年生の後半からは、GMOで6か月間アルバイトとして実務に参加しました。
実際のプロジェクトに関わる中で、チーム開発の進め方やコードレビュー、ユーザー視点を踏まえたUI改善といった「現場の開発プロセス」を経験しました。学生時代に学んだ技術を実務に適用しながら、新たに得た知見も多く、自分がフロントエンドエンジニアとして成長していける手応えを得ました。
まとめ
共通していたのは「自分の殻を破るために行動する」姿勢でした。他大学の人と話すことも、苦手な接客に挑戦したことも、資格に挑んだことも、すべては自分を広げるための一歩でした。
書いてみましたが「これをやらなきゃ」と縛られる必要はなく、いろいろ試して、失敗して、そこから学ぶことが一番大切です。大学は安全に挑戦できる数少ない時期なので、思い切って行動してみるのがおすすめです!