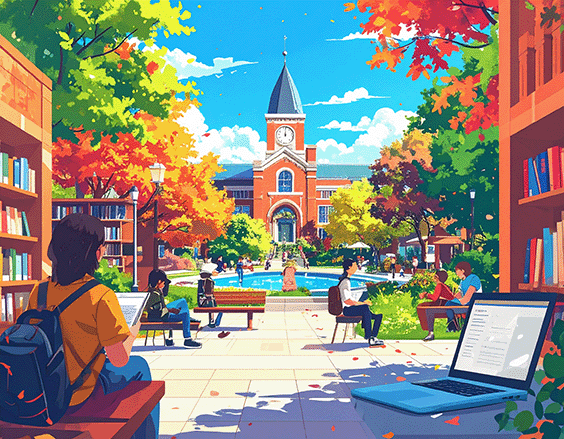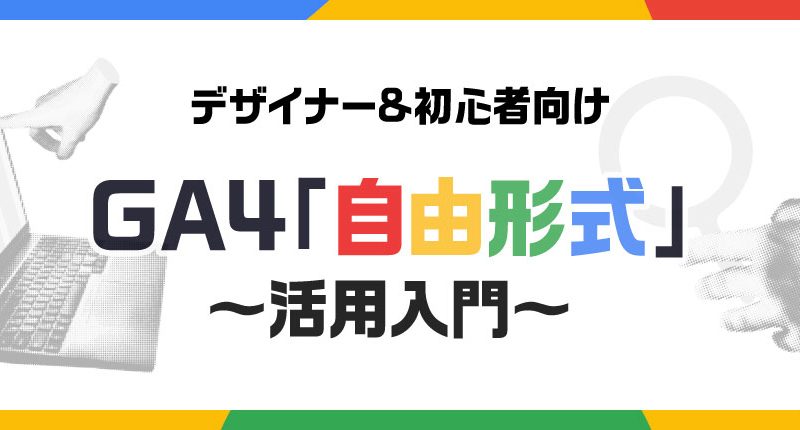「Web解析って数字とかグラフとか、ちょっと苦手…」と思っていませんか?
でも実は、デザインの“良し悪し”を数字で確かめられる超便利なスキルなんです。
どのデザインがユーザーに刺さっているのか、どこで離脱してるのか。解析を使えば、勘や感覚に頼らず改善できます。
この記事では、デザイナーが最低限知っておくと得するWeb解析の基礎を、ツールと一緒にやさしく紹介します。
Web解析の3つの種類
早速ですがWeb解析の種類は「サーバーログ方式」「パケットキャプチャ方式」「ウェブビーコン方式」の3つが存在します。
今回は簡潔にメリット・デメリットをまとめましたので、さらに詳しく知りたい方は調べてみてください!
サーバーログ方式
メリット:クライアント依存なし、全リクエストを記録、社内完結(セキュリティ◎)
デメリット:ユーザー行動の詳細は把握しづらい、ログ処理が手間
向いている人/状況:社内運用・セキュリティ重視の企業、インフラ寄りの管理者
パケットキャプチャ方式
メリット:実際の通信を取得、CookieやJavaScriptに依存しない
デメリット:専門知識が必要、HTTPS通信の解析に制限
向いている人/状況:ネットワーク管理者、セキュリティ・通信監視を重視する現場
ウェブビーコン方式
メリット:詳細なユーザー行動が取得可能、導入が簡単、ツール連携◎
デメリット:JavaScript無効ユーザーは非対応、Adブロックの影響あり
向いている人/状況:マーケターやwebデザイナー、Webサイト改善、コンバージョン最適化
多くの現場では「ウェブビーコン方式+Google Analyticsやヒートマップ」を使った 行動分析 が主流ですが、一部の大企業や金融・医療系では、サーバーログ方式で社内完結の解析を選ぶケースもあります。
セキュリティや正確性、目的ごとの使い分けが重要ということだね!
デザイナーにおすすめのWeb解析ツール4選

数ある解析ツールの中でも今回は基本無料で使用でき、リファレンス・情報が潤沢なものを、分野ごとに選定いたしました!
アクセス解析ならGoogleアナリティクス
Googleアナリティクスは、Googleが提供する高機能なアクセス解析ツールで、個人ブログから企業サイトまで幅広く利用されています。基本的には無料で使えますが、月間1,000万ページビューを超えると、有料の「Googleアナリティクス360」への契約が必要になります。
このツールを使えば、ページが何回表示されたか(ページビュー数)や、ユーザーがどれだけサイトに訪問しているか(セッション数)など、Webサイトの利用状況を細かく把握することが可能です。また、流入元やユーザーの行動パターンなど、マーケティングに役立つ情報も多く得られます。
ただし、機能が豊富な分、初めて使う人にとっては操作がやや複雑に感じられるかもしれません。それでも、解説サイトやマニュアルを参考にしながら学ぶことで、サイト改善や施策の見直しに活用できる非常に有用なツールと言えます。
表示速度解析ならPageSpeed Insight
PageSpeed Insightは、Webサイトの表示速度をスコア化して測定するための無料ツールで、WebサイトのURLを入力するだけで表示速度の解析をしたり、改善すべきポイントのアドバイスをもらえたりします。
そもそも、なぜページの表示速度を解析するのかというと、ユーザーの離脱率と関係があります。なぜなら、サイトをクリックして表示されるまでに時間がかかると、ユーザーはそのページから離脱してしまう可能性が高くなるからです。
実際にGoogleは以前から離脱率の改善を推奨してきました。このように、離脱率の低下はそのまま検索順位にも影響するので、Web解析をする上で見逃せない要素だと言えます。
pagespeed Insightを利用した実際の改善例とすると大きな画像は圧縮・WebP化して軽量化やフォントの最適化、大きな画像や動画を遅延ロードなどがありますね。
使用していない場合だと意外と気づかない細かい部分の修正ができる点が良いですね!
ヒートマップ分析ならUser Heat
ヒートマップ解析とは、ユーザーのWebサイトでの行動(熟読した箇所・クリックした箇所・ページを離れた箇所など)をヒートマップで視覚的にわかりやすく確認できる解析方法です。
User Heatで利用できるヒートマップは「熟読エリア分析」「クリックエリア分析」「マウスムーブ」「離脱エリア」の5つを確認できます。また、User Heatはスマホページの解析も可能です。
スマホの場合は、ページの上から下まで読まれる確率が高いなどPCとは異なる解析結果が出る可能性があります。
User Heatは月間30万PVまでなら無料で利用できるので、ヒートマップに興味がある人はぜひ試してみてください。
User Heatを利用した実際の改善例だとCTAボタンがあまりクリックされない → 色・サイズ・文言・配置を変更、スクロールヒートマップを利用して情報の精査・再配置などが考えられますね!
競合トラフィック分析ならSimilarWeb
SimilarWebは自分のサイトだけではなく、競合他社のWebサイトのアクセス状況を解析できるツールです。
無料版と有料版では機能に違いがあり、無料版は取得できる情報の期間が3ヶ月前まで、有料版は最大37ヶ月前までの情報を閲覧できます。
競合サイトがどのように集客して「なぜ成果を上げているのか」を把握することは、Webマーケティングにおいて重要な戦略の1つです。ただし、SimilarWebは独自の方法でデータを取得しているため、Googleアナリティクスが表す値と差が生じているケースがあります。
そのため、ページビュー数の調査には向きません。あくまで近似値としてデータを取得するので、競合他社のおおよそのデータを把握することに役立ちます。
Web解析の重要性と多角的なアプローチ

Web解析を効果的に行うためには、1つの解析ツールに頼るのではなく、アクセス解析・ヒートマップ・競合調査などを組み合わせることが欠かせません。
理由はシンプルで、ツールごとに得られるデータの種類や強みが異なるためです。
複数の手法を併用することで、自社サイトの改善ポイントを多方面から見つけ出し、検索結果で上位に表示されるための最適な戦略を立てることができます。
例えば、アクセス解析では訪問者数やユーザーの行動経路を把握できます。
さらにヒートマップ分析を使えば、ページ内でどの要素に注目が集まっているかを直感的に確認可能です。
加えて、競合分析を活用すれば、他社サイトと比較しながら流入経路や人気コンテンツの傾向をつかむことができ、自社の改善や戦略立案に直結します。
また、Webサイトの目的や状況によって必要なデータは変わるため、自社の施策に応じて解析方法を選び、最適な組み合わせを検討することがポイントになります。
Web解析の主なアプローチ視点
Web解析を行う際は、大きく分けて次の2つの視点から進めることが有効です。
・定量分析と定性分析
・自社サイト分析と競合サイト分析
この2つの軸を意識しながら柔軟に手法を取り入れることで、Webサイトの成果を着実に高めることができます。
定量分析と定性分析
▼定量分析
アクセス数、直帰率、コンバージョン率といった数値データを用いる方法です。
Googleアナリティクスのようなツールで収集した数値をもとに客観的に評価でき、割合や推移を正確に把握できます。
▼定性分析
アンケートやユーザーインタビュー、ユーザーテストなど、数値化できないデータを扱う分析手法です。顧客の具体的な声や体験を知ることができるため、定量分析では見えにくい改善点を発見できます。
数値データは理解しやすく再現性もあるため頻繁に使われがちですが、ユーザーのリアルな声を収集する定性分析も欠かせません。両方の手法をバランスよく組み合わせることが、課題解決や改善策の発見につながります。
自社サイト分析と競合サイト分析
▼自社サイト分析
自社サイトにトラッキングコードを設置し、訪問者数や行動データを収集するのが一般的です。アクセス解析によってユーザーの利用状況や流入経路を把握できます。
▼競合サイト分析
競合サイトには直接コードを埋め込むことができないため、専用ツールを利用して外部からデータを収集します。ツールによってはPV数、検索キーワード、流入チャネルなどを推定できるものもあり、自社との比較分析が可能です。
競合のデータを取り入れることで、自社サイトの課題がより明確になり、対策すべきキーワードやSEO戦略を見直すヒントが得られます。結果として、検索順位の改善やコンテンツ強化にもつながります。
Web解析は、アクセス解析・ヒートマップ・競合分析などを併用し、定量+定性、そして自社+競合という2つの軸から多面的に取り組むことが大切です。
単一の視点では見えない課題や改善策を発見できるため、成果を最大化するための有効な手段となります。
実際に商材の改善案なんかを考える際も、まずは上述のツールを使用し、例えば直帰率が高い場合は、ページのファーストビューを改善し、ユーザーの関心を引くコンテンツやデザインを導入したり、コンバージョン率が低い場合はCTAの位置や文言見直し、ユーザーがアクションを起こしやすい導線設計を行ったり、ユーザーがどのデバイスからのアクセスが多いかを確認し、デザインや機能の最適化を検討したりなど、その商材ごとに抱える課題や状況ごとに解決策を練っていきます。
まとめ
Web解析は、単なるマーケティング手法ではなくデザインの改善プロセスに直結するクリエイティブな分析です。
「なぜこのデザインにしたのか」を数字で説明できるデザイナーは、チーム内でも信頼されやすく、成果に直結する提案ができます。
「なぜ解析を行うのか」という目的を明確に持ち、複数のツールを組み合わせながらPDCAサイクルを回すことで、初めて成果を最大化することができます。
今回はWeb解析の種類とWeb解析のおすすめツール・アプローチ手法に関しての紹介でした!次回の記事でお会いしましょう!ばいばーい!